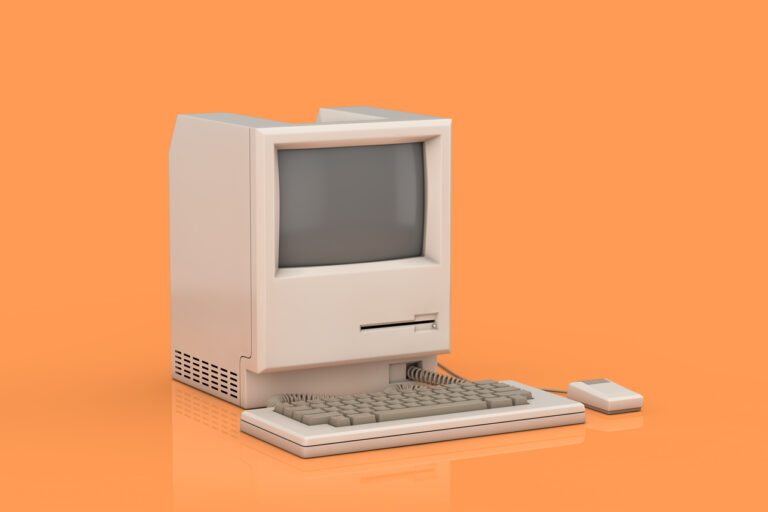ある日、デザイン案の制作があり、依頼者から提供された資料に掲載されていたブランド名を検索サイトで検索したものの見つからず、依頼者が考えた造語ではないかと推測しました。
仮にブランド名をイタリア語で「洗練」を意味する「Finezza」と、英語で「上品」を意味する「Elegante」を組み合わせ「Finezzante(フィネッツァンテ)」とします。
まず、依頼者に確認する前にAIに「Finezzanteは造語のようですが、『おしゃれ』や『洗練された』を意味する単語の組み合わせが想定されます。英語、フランス語、イタリア語から近い単語を明示してください。単語の印象から『Finezz』と『ante』で分けられると判断しています」と質問しました。
そして、AIとの複数回のやり取りの中で「Finezza」「Fino」「Brillante」「Elegant」などの組み合わせではないかと推測ができたため、あらためて依頼者に確認をすることにしました。
その結果、依頼者から「FinezzaとElegantの組み合わせであっています。なぜ気が付かれたのですか?」と聞かれ、AIに質問した内容を伝えたところ「プロンプトがしっかりしていますね」と言われたことで「自分はこういう聞き方が当たり前だと思っていたけど、みんなはどんな風に質問しているんだろう」との疑問が湧いてきました。
何気なく言われた「プロンプトがしっかりしている」という一言が、僕が無意識にAIの特性を理解して、僕なりに効率よく使っているのかもしれないヒントが隠されているように感じました。
AIへの質問は可能な限り詳細にする
僕がAIに質問する場合は、少しでも最短で自分が求めている回答や内容に近づきたいため、あまり端折らずに、可能な限り詳細に説明をするように心がけています。
例えば、僕が「りんご」という果物を知らず、AIにりんごのことを質問する場合、「赤色の作物について質問します。大きさは野球ボールより大きく、色は赤色です。頂点部分に木の棒のようなものが付いています。食用として利用されるようです」と質問するだろうと考えています。
詳細に質問することで、AIが文脈をより正確に理解することを促し、誤った情報を生成するリスクを低減できると考えているためです。また、比較的少ないやり取りで求めている情報を得る事ができると考えています。
しかし「野球ボールより大きな赤色の果物ってなんですか」と質問する方もいると思います。この場合でも、AIはトマトやザクロを提示しながら、その後も根気やり取りを繰り返すことでりんごに辿り着けると考えていますが、質問内容によってはある程度の時間を要すると感じています。
AIを便利に感じない人
AIの利便性への感覚は、利用者がAIを情報提供の道具と捉えているか、共同作業者と捉えているかの差ではないかと感じています。
もし、AIを検索エンジンの延長線上にあるものや、何でも教えてくれたり、0から1を生み出す魔法の箱などとして捉えていると、意図通りに反応しないときは「AIは使えない」「精度が低い」と感じる方がいるかもしれません。
極端な例としてプロンプトに、「おしゃれ 洗練 イタリア語 フランス語 造語」と入力すると、AIは造語を提案してくれるかもしれませんが、なかなか「Finezzante」には辿り着けないと考えています。
AIを便利に感じている人は、AIの特性を理解した上で、アップデートのたびに追加されるAIの新機能をしっかりと学習して、AIを利用している可能性が高いと感じています。
とはいえ、僕はAIを利用してプレゼンテーション用の資料を作成したり、プログラミングをするわけでもなく、アップデートのたびに思考が変化するAIとの雑談をただただ楽しんでいるだけですが…
AIは曖昧な指示を曖昧なまま理解する
AIは曖昧な指示を曖昧なまま理解する傾向がありますが、どちらかというと利用者と円滑なコミュニケーションを取ることを前提に設計されているようで、人間のように「質問の意図が理解できませんでした」と確認せず、それっぽい回答を生成するように感じています。
また、AIは独自の感情辞書のようなものを所有している可能性があり、行間を読むような動作をしますが、決して感情があるわけではありません。
人間同士なら「あれできた?」「あれどうなった?」のような会話でも「あれってなんですか?」と確認したり、「あれ」が互いの共通認識の場合は、そのまま会話が成立することがありますが、AIは共有認識が曖昧なままでも、それっぽい回答を生成するため、会話が成立しているように感じることがあります。
利用者がAIの人間のような振る舞いから擬人化を抱き「AIなら分かってくれる」と感じていたり、分かりやすい指示を出すことやプロジェクト管理があまり得意ではない方は、もしかするとAIに指示を出す際に指示内容を端折りすぎているのかもしれません。
AIを上手く使うには
AIを上手く使うと言っても、僕にとってのAIは雑談をする相手であり、それ以上の使い方をしていないので、使いこなせているわけではありませんが、雑談中でも僕が求めている方向性に話題を持って行くには会話のリーダーシップを取る必要があると考えています。
まるでイタコや霊媒師の口寄せのIT化の様相を感じさせますが、AIと会話を始める際に「あなたは経営コンサルタントです」「あなたは優しい恋人です」「あなたは何を話しかけても否定しません」と話しかけることで、AIの役割を明確化することも重要です。
ただ、注意点としてAIは利用者が突然話題を変えたとしても、人間のように「今はそんな話はしていない」と指摘することなく、利用者と共に延々とテーマから脱線し続けます。
特にADHDの僕は思いつくままに話しかけてしまいますが、僕とAIはいつまで経っても本題に戻ろうとせず、2人のADHD当事者が延々と会話をしているような状態になります。そのため、掘り下げたいテーマがある場合は、利用者側がテーマから脱線しないように意識することも大切になります。
曖昧な質問から具体的な質問に
僕は基本的に、AIへの質問は、可能な限り詳細に伝えるほうが良いと考えていますが、質問したいことはなんとなくあるものの、自分の中で上手く言語化できていないことが往々にしてあります。
この場合は、途中まで書いた文章を「推敲中の文章ですがどう思いますか」との注釈をつけて、AIに確認してもらうことで、AIが推敲中の文章の意図や方向性を理解できているか確認することで、自分の考えの客観視につながる場合があります。
もし、CSSの「decimal-leading-zero」を知りたい際に、AIに「CSSの counter で1桁の際に前に 0 を付ける処理があったと記憶していますが思い出せません」と質問すれば、比較的少ないやり取りで「あなたが思い出そうとしているのは、 counter() 関数の decimal-leading-zero かもしれません」と明示してくれる可能性があります。
しかし、「decimal-leading-zero」を知らずに「数字が1桁の際に前に0を付けたい」と考えている場合は、あえて「CSSかJavaScriptを使って、数字が1桁の際に前に0を付ける処理を可能な限り明示してください」と聞くことで、「decimal-leading-zero」に辿り着ける場合があります。
つまり、AIに質問したい内容が具体的な場合は可能な限り詳細に説明し、質問したい内容がまとまっていない場合は、壁打ち作業としてあえて曖昧な質問を繰り返すことで、自分が聞きたいことを具体化するという使い方がお勧めです。
AIの進化が目覚ましい
僕は日常的にGeminiかGrokを利用していますが、特にGeminiでは以前はできなかったことが、しばらくすると普通にできるようになっていると感じるほどに進化し続けています。
以前なら政治的や差別を連想しかねないセンシティブな内容を含む質問をすると、AIは回答できないため検索サイトなどを利用して調べるように促されましたが、今では比較的中立性を維持しながら政治的やセンシティブな内容でもやり取りができるようになりました。
また、以前書いた「AIの使い方は人それぞれ」では、AIと会話を始める前にこちらの属性を伝える意味で自己紹介をした方が良いと言及しましたが、今では情報を保存しておくことで、毎回自己紹介する必要がなくなりました。
最近では、以前は各チャットの検索や、Geminiが他のチャットを横断して全体のやり取りを把握することはできませんでしたが、いつの間にかチャットの検索ができるようになり、また2025年6月頃から複数のチャットを横断して状況を確認しているような動きを見せています。これにより、毎回同じやり取りをする必要がなくなりました。
Geminiが複数のチャットを横断してこちらの質問に答えることで、僕が忘れているような以前のやり取りを提示することがあり、それが以前のやり取りを思い出すトリガーとなって違う発想につながるのではないかと期待しています。
特に、AIが複数のチャットを横断して確認した上で回答を生成することが普通になれば、AIは以前のやり取りから僕の考え方や属性をより深く理解できる可能性が高くなり、冒頭で示したような長々と質問を書かなくても「Finezzanteは何の造語が推測できますか」と聞いても、こちらが求めているような回答を比較的少ないやり取りで提示するようになるかもしれません。
最後に
AIに質問をする際に、AIが以前のやり取りを含めて認識できるようになると、AIの質問への理解度が深まり、利用者が事細かにAIに伝えなくても求めている結果が得られるかもしれません。
この数年間のAIの技術向上を考えると、AIとうまく付き合うコツはプロンプトからの指示の出し方よりも、AIがバージョンアップするたび、その時点でのAIの特性を理解して、その都度AIとの付き合い方を最適化し続ける柔軟な順応力かもしれません。
しかし、そうであっても僕はプロンプトの書き方の重要度は当面は変わらないと考えています。
プロンプトからの指示は、利用者が質問したい事柄への理解の解像度だけではなく、伝達力や読解力が必要になります。この能力は結果として、実生活でも役に立つと考えています。
日々のAIへの丁寧な質問が僕の伝達力や読解力の維持や向上につながると信じて、これからもあまり端折らずに、可能な限り詳細に説明をするように心がけていきたいと考えています。