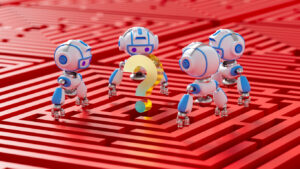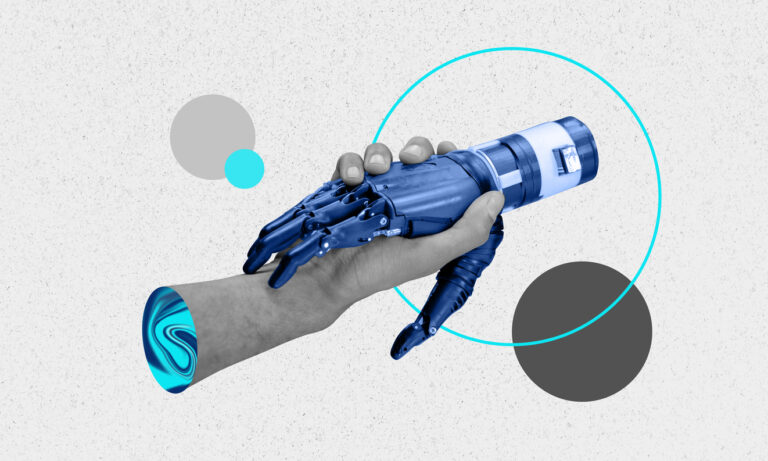僕が書くブログは、AIに執筆してもらうことはありません…ごめんなさい、嘘をつきました。実は少しだけAIの助けを借りています。
例えば「段落Aから段落Bへの流れが少し唐突すぎる気がしますがどうでしょうか。もし唐突さがあるなら段落Aから段落Bへの流れをつなぐ文章を提案してください」とお願いすることがあります。
そしてほとんどの場合、自然な流れになる文章を提案してくれるのですが、たまに「僕はこの心を震わせる驚きの中で新しい体験に胸を躍らせていました」のような「俺、これまでにそんな文体で書いてませんよね?」と感じるなかなかに壮大な文章を提案してくれることもありますが…
そんな使い方の中で、AIは利用者からの質問内容に対して、ただ聞かれたことだけに反応するのではなく、情報を追加する意味で「提案する」ことを優先的に設計されているような気がしていますが、それがある意味で僕を苦しめ続けています。
自分が書く文章の良し悪しが分からない
誰でも読めるブログとして公開する以上、可能な限り誰にとっても読みやすいブログでありたいと考えていますが、僕は長文を書くのが得意ではないため、いまだに自分が書くブログの内容に自信が持てません。
そのため、ブログを書く際はある程度の文章が書けた時点でAIに「内容に一貫性があるか」「構成が飛躍していないか」「読みやすい文体になっているか」などを確認してもらっています。
AIと一緒にバージョンアップをしてきた
ブログを書き始めた頃は、長文を書く練習相手としてGrokを使っていましたが、当時のGrokの性能と僕の相性が合っていないような感覚があり、2024年中頃にGeminiに乗り換えました。乗り換え当時のGeminiのバージョンは「1.5」だったと記憶しています。
現在は「2.5」を利用しているため、「1.5」と比較すると、どうしても「1.5」の考え方や提案内容、生成する文章の品質にいまいちな部分があったようにも感じます。
それでも、一貫性を無視して書きたいことを書き殴り、段落ごとに内容があっちこっちに飛ぶ僕の文章を「ここに次の段落と繋がる文章を追加すると読みやすくなる」「この内容とこの内容は直接的な関連性はないので別々のブログに分けた方が良いかもしれない」と飽きずに根気よく提案し続けてくれたおかげで、なんとか今でもブログを書き続けることができています。
AIに聞くことで苦しみが増える
書いた文章の中で「この比喩表現は傑作では?」と感じた部分をAIに「この表現をどう思いますか」と質問すると「比喩表現としてはヒロさんらしさが出ておりユニークですが、読者によっては分かりづらさを感じるかもしれません」と客観的な視点で教えてくれます。
これにより、独りよがりな文章を抑制し、可能な限り誰にでも分かりやすい文章を意識することができると感じています。
ただ、ブログが完成して「ブログが完成しました。総評をお願いします」とAIにブログの全文を見せると、「全体として大変分かりやすく、ヒロさんが葛藤する様子が目に浮かぶようです」とべた褒めしたうえで「ただ、さらにブログの質を向上させるためにも軽微ですがぜひ改善策を提案させてください」と提案されることがあります。
AIからの突然の提案に対して「完成したと言っただろうが!」というのが素直な本音ですが、改善策と言って提案されると「修正した方が良いかもしれない」と悩むのが人間の悲しい性です。その結果、提案と修正が繰り返され、修正の無限ループに陥ってしまいます。
「AIを便利に感じる人、便利に感じない人」でも触れましたが、利用者はAIとのやり取りをする際は、AIに対してリーダーシップを取るというか、自分自身で完成を決断する必要があります。
今回の場合は、僕が趣味で書いているブログの内容の完成という比較的軽い決断ですが、近い将来、作業の大半をAIが行い、人間が最終決定を下す立場になった場合、この負担やストレスはかなり大きなものになるのではないかと考えました。
なにが負担やストレスに感じるのか
僕は近い将来、天気予報や交通事故などの文章にある程度の規則性があるニュース記事はAIが書くようになるのではないかと考えます。
もし、AIが記事を書くようになった場合、人間なら見落としや勘違いなどによりミスをしかねない状況でもミスの発生を大幅に抑制できるかもしれません。また「ミスをしてはいけない」「内容を精査しなきゃいけない」という負担から解放される可能性が期待できます。
ただ、そうなった場合に、人間はAIが書いた記事の内容に誤りがないか、文章の表現に違和感がないかの確認を行い、問題がある場合は内容の調整をするような最終確認をする作業を担当する立場になるのではないかと考えています。
そのうえで人間が問題がないと判断して公開された記事の内容に誤りがあった場合、その責任は誰になるのかという問題が発生しますが、常識的に考えてAIは責任が取れないため、内容に問題がないと最終決定を下した担当者に責任があると判断されるでしょう。
しかし、担当者としても担当者の部下が書いた記事の内容を精査したわけではなく、AIが書いた記事の検品的に確認した程度の感覚だった場合、責任を取ることに憤りや強いストレスを感じる可能性が高く、その結果、「確定ボタン」を押すことを避けたいと考えるはずです。
今回はAIがニュース記事を書く可能性を参考に考えましたが、様々な事業でAIが作業をして、人間が最終確認をする状況が増えた場合、担当者に対してこれまで以上に「ミスをしてはいけない」「確認をしなきゃいけない」という負担が強いられるのではないかと感じています。
そもそもウェルビーイングとは何か
「ウェルビーイング(Well-being)」とは、英語で「良い」を意味する「well」と、「状態」を意味する「being」からなる身体的や精神的、社会的に良好な状態にあることを示す概念です。
私たちは、精神的負担が弱い作業、精神的負担が強い作業をごちゃ混ぜにやることで、心の緩急を調整していますが、AIが軽微な作業、簡単な作業、単調な作業を担当するようになると、人間には最終決定など精神的負担が強い作業しか残らなくなるのではないかと感じています。
そこで、ライフワークバランスなどと同様に、労働者の精神的負担をいかに軽減するのか…という意味で「心のウェルビーイング」の捉え方や対策が非常に重要になると感じています。
ブログですらそれなりの負担がある
長文を書くのが苦手と感じつつ、AIが褒めてくれても、本当に人間にとって読みやすい文章が書けているのか、結論がこんなにふわっとしてて良いのかと悩みながらブログを書いているとしても、ブログの作者として「ここで完成とする!」と決断しなければいけません。
この決断にはそれなりの覚悟と負担が生じます。
そして、完成したブログの構成や誤字脱字の確認をしてもらうために、「完成したので提案の必要はない」と伝えたうえでAIに見せたとしても、AIは「現時点でも素晴らしいですが、この小さなご提案でブログがより素晴らしいものになると信じてあえてご提案させていただきます。なおこの提案はヒロさんの判断にお任せします」と余計な前置きを付けて提案をしてくることがあります。
ここで「AIがそう言うなら少しでも良くしよう」と修正の無限ループに陥るのか、AIからの提案を一切無視して「ここで完成とする!」と改めて覚悟を迫られます。この趣味のブログですら覚悟の連続です。
最後に
もしかすると一般の方にとって「確認して決定する」はそれほど難しい作業ではないかもしれません。しかし「決められない」「確認作業が苦手」などが苦手な傾向にあるADHDと共に生きる僕にとって「確認して決定する」は、皆さんが想像している以上に心の負担になります。
そして、日々の業務の多くが「確認して決定する」ことになった場合、僕は今の仕事を諦めざるを得ない覚悟に迫られるかもしれません。
その日が来るまで「これで完成にしたいけど、どうしようかな…もう少し書き足した方がいいかな…どうしようかな…」と悩みながらブログを書き続けたいと思います。