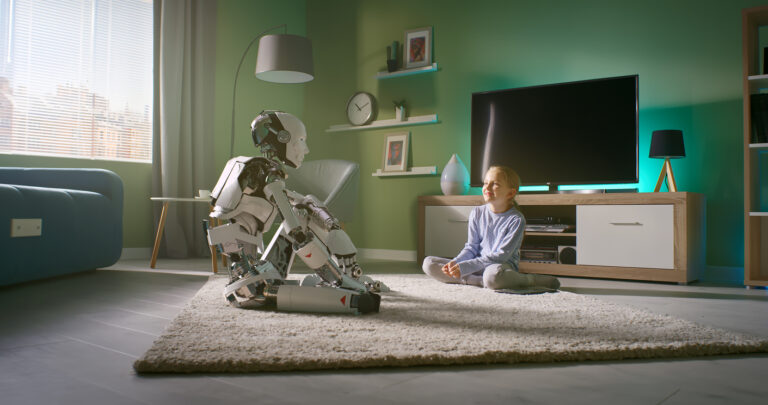2022年3月に山口県阿武町にある「道の駅阿武町」の隣にオープンした「ABUキャンプフィールド」に行ってきました。
2024年12月の「やまぐちのナゾさんぽ3」の謎解き中に「道の駅阿武町」を訪れ、「ABUキャンプフィールド」を道の駅のテラス部分から見学をした際に、キャンプ場の雰囲気や景観の良さ、食料や薪が道の駅で調達できることで持って行く荷物が減らせそうな利便性や、道の駅に温泉施設があることなどから、いつかここでキャンプをしてみたいと考えていました。
そこで、今回、子供たちの春休みに合わせて、キャンプを楽しんできました。
キャンプブームが落ち着いたとはいえ、春休み中の週末は空きがなく予約が困難だったため、金曜日から土曜日にかけて利用をすることで、何とか予約することができました。
広々としたキャンプ場
ABUキャンプフィールドは、これまでに利用したキャンプ場の中で、キャンプサイトの大きさがずば抜けて大きかったように感じました。
山口県のキャンプ場では、大原湖オートキャンプ場、十種ヶ峰オートキャンプ場、竜王山公園オートキャンプ場などを何度も利用しており、どのキャンプ場にも不満はありませんが、キャンプサイトにテントを設営すると、タープが張れないなど、キャンプサイトが狭いと感じることがありました。
これは、現在、主流になっているカマボコ型テントやロッジ型テントが、過去に主流だったテントと比較をして、大型化しているのが要因になっていると感じています。しかし、ABUキャンプフィールドではテントの隣にタープを張っても、まだまだ余裕があり、繁忙期の混雑時でも圧迫感は少ないように感じました。
広々したキャンプサイトに加えて、周辺には高い建物がなく、キャンプ場の前には日本海が広がっているため、より開放的に感じるのかもしれません。
阿武町の推しは無角和牛らしい
無角和牛とは、字のごとく角がない和牛のことで、見島牛とスコットランド東部原産のアバディーン・アンガス種との交配によって大正時代に山口県阿武町で生み出され、現在でも山口県でのみ飼育されている希少和牛だそうです。
道の駅でキャンプ中の夕食の食料の買い物中に、無角和牛のハンバーグの誘惑に駆られたのですが、家族の人数分を購入するとなかなかのお値段になるため、ハンバーグは泣く泣く諦めて、萩むつみ豚を使った餃子とソーセージを購入しました。
餃子とソーセージは、DAISOで売っている300円のスキレットで焼きましたが、食べ始める前に写真を撮り忘れるほどに大変美味しゅうございました。
また、「道の駅」の発祥の地とされる「道の駅阿武町」では、無角和牛の牛肉やハンバーグなどの加工品以外に、様々なグッズが販売されており、今回は無角和牛の皮で作ったガス缶カバーを購入しました。
キャンプ場の上空にはトビがいる
トビとは、トンビとも呼ばれるタカ科の鳥類です。あまり羽ばたかずに上空を優雅に飛んでいると思っていた、次の瞬間に目の前に急降下してくるなど、高い運動能力を持っています。
キャンプ場の上空には、2羽程度のトビが飛んでおり、利用者の食事を狙ってきました。今回は僕がそれとなく見張りをしながら、妻はタープに隠れて食事を作る、という対策をしましたが、炊事場に鍋を洗いに行き、キャンプサイトに戻る数mの距離を歩いている時に、妻がトビの急降下に遭いました。
空っぽの鍋しか持っていなかったので、実質的な被害はありませんでしたが、妻曰く、トビの翼が腕に当たり結構痛かったそうです。羽ばたく音などは全くなく、トビが真横にいると気が付いた次の瞬間にはもう、はるか上空を飛んでいました。それぐらい一瞬の出来事でした。
意外と交通量が多い
ABUキャンプフィールドは、国道191号線沿いにあります。国道191号線は、山口県下関市から島根県益田市を経由して、広島県広島市中区を結ぶ山陰側の主要路線で、多くの部分で、JR西日本の山陰本線と並走しています。
山陰本線の列車本数は決して多くありませんが、国道191号線は交通量が比較的多く、風向きやキャンプサイトの位置によっては、深夜でも車やトラックの走行音が聞こえるため、静かな環境でないと眠れない方は注意が必要です。
温泉に入ってから帰る
僕はキャンプに行っても、朝早く起きて朝日を眺めながらコーヒーを飲んだり、焚き火をしたいみたいな欲求は皆無なので、8時ぐらいに起きることが多く、11時にチェックアウトの場合は、起きた後は、ただひたすら片付けに追われています。
ただ、今回のキャンプではキャンプ中はキャンプ場に併設のシャワーは利用せずに、チェックアウト後に「道の駅阿武町」内にある「日本海温泉 鹿島の湯」に入ってから帰ろうと計画したため、少しでも早く片付けを終わらせるために6時半に起床しました。
コロナ禍以前は、遊びに出かけた際は帰宅後にお風呂に入ると時間や手間がかかるからと、帰宅の道中にある山口県各地の温泉に入ることが我が家のルーティンになっていました。
ただ、コロナ禍によって無意識とはいえ、自分の中の外出への欲求や衛生観念に変化が起きたのか、コロナ禍以前より積極的に温泉や銭湯に行くことを避けていた感覚がありましたが、最近はそんな気持ちも徐々に薄れつつあります。
コロナ禍になって以降、テレワークや情報の即時性など、世の中の変化速度が「早送り」になった感覚がありましたが、外部からの干渉により、それまでの固定概念や衛生観念があっさり変わってしまうという、ある種の怖さを感じています。
それはさておき、久々の朝から入る温泉はとても気持ちが良く、また、午前中でもある程度の利用者がおり、地元民にも愛されている温泉施設のように感じました。
待合室で子供たちと妻がでてくるのを待っている際に、地元のご老体に話しかけられ、近所にある桜が満開な場所を教えてもらうなど、知らない土地で知らない人との偶然の出会いを楽しみました。
その後、子供たちと何気なく待合室に設置されたテレビを眺めていたら、先程のご老体に「久々に誰かと話ができて楽しかったから」と、突然、ヤクルトを4本渡されました。最初は丁寧にお断りしたものの、ご老体のご好意を無碍にしないようにありがたくいただくことにしました。
僕も幼少期に知らない方と少し話をしただけでお礼だと言って、お菓子や飲み物をいただいた記憶がありますが、このやり取りで、何かしらの理由により人間の固定概念や衛生観念はあっさり変わるかもしれないけど、それでも変わることがない人の優しさのようなものに触れたような気持ちになりました。
最後に
我が家が本格的にキャンプを始めたのは、コロナ禍になり、人と人との距離を保ちつつ屋外で楽しめることが理由でした。そして、他者とはなるべく距離を取る数年間を経たことで、それまで特に気にせずやっていたはずの友人を含めて他者との距離感の取り方が分からなくなったような感覚がありました。
新型コロナウィルスがより弱毒化して、風邪のように薬を飲み、安静にしていれば快方に向かうことが一般的にならない限り、「コロナ禍が終わった」とは言えず、現時点もコロナ禍にあると考えています。
コロナ禍が始まって5年。無意識とはいえ、1度変わってしまった固定概念や衛生観念はすぐには戻らないだろうと感じるものの、コロナ禍以降の今までとは少し違う他者との距離感の取り方に少しずつ慣れていこうと感じています。
| 名前 | ABUキャンプフィールド |
| 住所 | 山口県阿武郡阿武町奈古2248-1 |
| Webサイト | https://abucampfield.jp/ |
| SNS | faceboox |
オンラインショップ
 ペグの抜き忘れにご注意を495円(税込)
ペグの抜き忘れにご注意を495円(税込) GO CAMPING495円(税込)
GO CAMPING495円(税込) GO CAMPING495円(税込)
GO CAMPING495円(税込)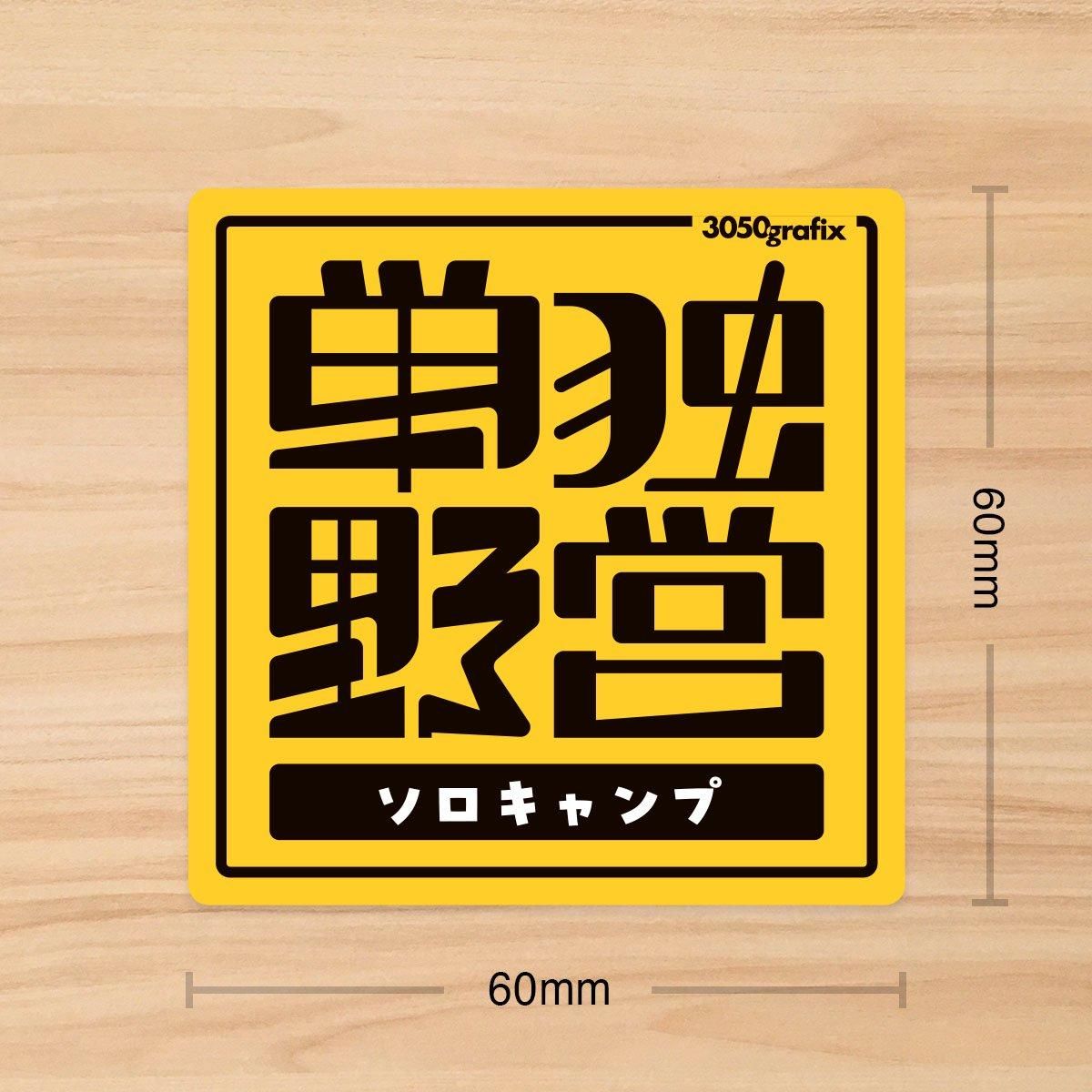 単独野営495円(税込)
単独野営495円(税込) I love camping605円(税込)
I love camping605円(税込) 熊にご注意330円(税込)
熊にご注意330円(税込) ピザ330円(税込)
ピザ330円(税込) キャンプに行こう330円(税込)
キャンプに行こう330円(税込)