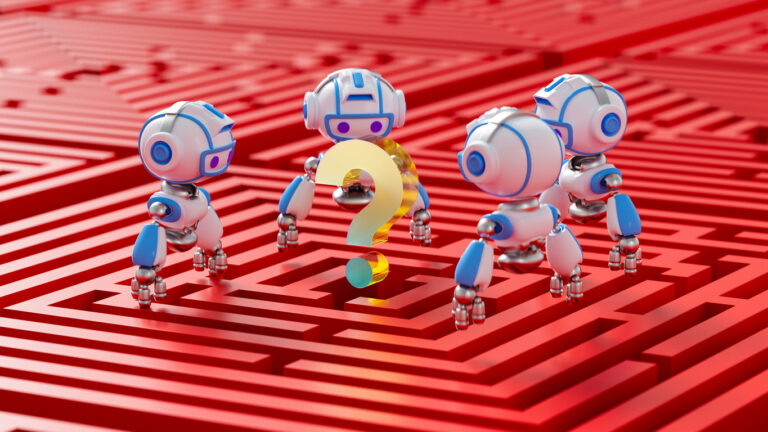僕が学生の頃は、世間には今と比べて「ぼっち」が忌避される空気感がありましたが、ADHDと共に生きる僕の行動には衝撃性が伴うため、一旦、自分の中で「週末に行く」と決めてしまうと予定の変更には苦痛が伴います。
そのため、僕が「行きたい」と思ったタイミングと、友人の予定に合わせるぐらいなら1人で行くほうが良いと考えて、学生時代から映画館や博物館などは、ほとんど1人で行っていました。
つまり、僕は若い頃から、他人への干渉も、他人からの干渉も避け、「うちはうち、よそはよそ」という感じに行動をしていたように感じています。
そんな僕が勉強会をやってみたいと思った
しかし、そんな僕が大阪府から山口県に引っ越しした2010年頃に、Web勉強会と称した集まりを企画、参加への呼びかけをしたことがありました。
2010年頃、IT関係者の間でTwitter(現X)の利用が浸透しつつあり、都市部で開催されるTwitterでは様々な勉強会の様子が流れていました。
都市部や地方都市に関係なく、今の情報を瞬時に触れる状況が整いつつあった事で、距離などの問題から都市部の勉強会には参加できない地方都市の技術者が近場で「集まって何かをしよう」という機運が醸成されつつあったように感じています。
僕の無意識下に「都会から田舎に引っ越しをした僕がWebサイトの勉強会を開催しますよ」という邪な気持ちがなかったかというと断言できませんが、たまたまそんなタイミングで、僕はTwitterで「勉強会みたいなものをやってみたい」とツイートしたところ、様々な方のご協力を得て「山口県WEB勉強会」を実施することができました。
ただ、ADHD特有の衝動性で声掛けをして始まった勉強会が、「毎回、参加者の顔ぶれが変わらないからもうやらなくても良いのでは…?」と感じて、ADHD特有の飽き性も相まって、数回の開催後にすっと手を引いたのは今となっては、心よりお詫び申し上げる次第です。
勉強会のフリをした友達探しだった
参加者の皆さんの思いや考えはさておき、僕としては何か得るための「勉強会」ではなく、大阪府から「ふぐ」と「明治維新」程度の情報しか知らずに引っ越しをしてきた山口県で、Webサイトの制作に携わる友人を探すというのが本当の目的でした。
また、「毎回、参加者の顔ぶれが変わらないなら、もうやらなくても良いのでは…?」と考え始めたのが、僕にとっての気持ちの変化の取っ掛かりだったことは事実です。
しかし、山口県の引っ越し直前に長男が生まれ、勉強会の開催前後に次男が生まれ、在宅の個人事業主として生きる僕にとって、自分の人生の立場が急激に変化していました。
これまでなら妻に「ちょっと勉強会に行ってくる」と伝え、2、3時間の勉強会の後に8時間の飲み会をやっていたとしても何の問題もありませんでしたが、妻1人に小さい子供2人の相手をさせるのは如何なものか…と考えるようになり、無意識に外出を避けるようになっていたのかもしれません。
子育てが少し落ち着いた
それから、数年間は知人や友人とのBBQや勉強会などの集まりに参加することはほとんどありませんでした。
僕が参加を止めても、その後も勉強会が開催され、皆さんの楽しそうな様子をSNSを介して眺めるのは正直しんどい時期もありました。それでも、ただひたすら子育てと仕事に明け暮れる日々を過ごしていました。
あの瞬間は、自分でもよく分かっていませんでしたが、時間の経過とともに僕が「移住者」「制作者」という立場から「個人事業主」「父親」「山口県民」という立場に変化をする中で、自分の時間がうまく使えなくなるという、人生のステージの変化だったんだろうと感じています。
「2025年の阿知須浦まつりが終わりました」や「家にいるけど暇じゃない」でも触れましたが、子育てによって、山口県の同業者との関係は希薄になったものの、勉強会に参加できない間も、自治会や商工会の役員、子供たちが通う学校のPTAの役員に携わり、社会との接点が断ち切れていたわけではありません。
しかし、そういう場所で知り合った方々とは仕事の「あるある話」ができないという物足りなさは、どことなく感じていました。
それから時間が流れ、子供たちが小学校高学年になった頃から、少しずつ自分の時間を持てる機会が増えてきました。
「よし!また勉強会に参加できそうだ!」と感じ始めていた矢先にコロナ禍が襲来し、人間同士の接触が大幅に制限され、勉強会への参加どころではなくなりました。
今もコロナ禍真っ只中だとは思うけど…
2020年に始まったコロナ禍が2025年になって落ち着いたとは感じておらず、現時点でもコロナ禍の真っ只中にいるとか考えていますが、それでも「三密」と言われていた頃に比べて、社会がコロナ禍以前を取り戻すように動き始めていると感じています。
しかし、コロナ禍というか、生命の存続が危ぶまれる非常事態では、人間の考え方が変容する速度が加速するように感じていました。
コロナ禍を経て、僕を含めて様々な方の考え方は確実に変容しており、また世代間の考え方の違いもあり、無理をして集まらなくても良いという前提が生まれ、組織でのイベントや飲み会などは減少傾向にあるようにも感じています。
勉強会そのものは動画配信サービスの登場により参加への障壁が下がり、増加傾向にあるとしても、オンラインでの参加によって、勉強会後の挨拶を兼ねた異業種交流会としての要素は大きく変化していると感じています。
オンライン活用の普及によって「無理に集まる必要はない」という空気が定着しましたが、これは単なる感染対策だけでなく、以前から潜在的にあった「その集まりは本当に必要なのか?」という疑問が顕在化したようにも思えます。
そして、この「集まりの必要性」を問い直す動きは、よく言われる「若者の飲み会離れ」などに見る、世代間の価値観の違いとも、どこかリンクしている気がします。
世代間格差は存在する
世間が勝手に決めた区分で言うなら僕は氷河期世代になりますが、僕は同世代との「飲みニケーション」は嫌いではありませんでしたが、上司との「飲みニケーション」は好きではありませんでした。
でも、上司との互いに酔わずにしっかりと意見が言い合える食事を伴うコミュニケーションは嫌いではありませんでした。
氷河期世代の僕がZ世代の方の意見や気持ちを代弁できるとは思いませんが、Z世代の方々も単純に「飲みニケーション」が嫌いなのではなくで、飲みニケーションの好き嫌いに彼らなりの考えがあるんだろうと感じています。
結局1人では生きていけない
インターネットの普及期(成長期)から成熟期の初期にかけて「インターネットがあれば場所を問わずどこでも仕事ができる」と言われ始めた時期がありましたが、実際は目に見えて大きく変化はしませんでした。
コロナ禍を経てテレワークは浸透し、ある程度は定着しており、政府の方針などからテレワークが完全に廃止になることはないと考えていますが、それでも業種によっては出社回帰や完全なテレワークから週3日以上出社のハイブリッドワークに移行している企業も少なくありません。
僕個人としては、人間は進化の過程で過酷な環境を向社会的行動で乗り越えてきたと感じており、技術の進化によっていつでもどこでもやり取りができるようになっても、週に数回でも対面でやり取りをしないと仕事がうまく進まないのではないか、と考えています。
コロナ禍以前からもテレワークやオンラインミーティングで問題のない業態は存在していたはずですし、コロナ禍によってテレワークやオンラインミーティングが定着したからといって、無理にそれらを対面形式に戻す必要はないと考えます。
ただ、AIの登場以前から「1人ブレインストーミング」で考えをまとめてきた僕にとって、AIではなく、気が知れた友人たちとの取り留めもなく、グダグダとした会話から気がつく発見は少なからずあると感じています。
AIの登場により誰かと調整をしなくても「思考の壁打ち」「ブレインストーミング」が24時間365日いつでもできるようになったことで、今まで以上に「ちょっと誰かに聞いてみよう」と考えることが減ったことに強い不安を感じています。
人生のステージは残り時間が気になる段階へ
とはいえ、僕のSNSのタイムラインは急速に高齢化しており、僕もアラフィフという不安しかない人生の階段を息を切らしながら駆け上がっています。
また、40代になり、すでに数年前には折り返しているであろう自分の人生を見つめながら、20代の頃に比べて、明るい未来よりは人生の残り時間が気になり始めています。
それにより、なんとなくリニア中央新幹線や北陸新幹線、山陰自動車道、下関北九州道路が僕が生きている間に全線開業することは不可能だろうとなんとなく悟りつつあります。
僕の生きる世界がシムシティの世界なら、一瞬で完成に立ち会えただけに本当に残念です。まぁ、この世界がシムシティの世界なら僕の人生も一瞬で終わりますが…
ご老体たちは何を思うのか
「漠然とした未来の話をしよう」でも触れましたが、歳を重ねることでこんなにも考え方が変容するのかと思うと、明日、死んでもおかしくない年齢に達している地区のご老体は何を思いながら草刈りをしているのか…と考えることがあります。
ただ、ご老体を見る限りそんな哲学的なことは考えているようには見えず、きっと「腰が痛い」とか「毎年、草刈りしてる…」ぐらいしか考えていないような気もします。
仮に哲学的なことを考えているとしても、せいぜい「人間は考える葦である、目の前にあるのは毎年、伸びる草である…この草刈りは何時に終わるんだろう」ぐらいだろうと思います。
最後に
僕は週末ごとにイベントへの出店や山口県を舞台にしたリアル宝探しに忙しくて、なかなか人間関係を広げたり、自分を研鑽する集まりに参加できずにいます。
また、僕がPCを触り始めた1995年頃はPCやHTMLタグなどは独学で習得するという雰囲気があり、僕の中でその傾向は今も変わらず、今でも自分を研鑽するという意味での勉強会にはあまり進んで参加をしていません。
ただ、昨今のブラウザや開発環境の変化は目覚ましく、プログラミングやコマンド操作ができない僕にとって、正直どこまでついていけるか不安しかありません。
ADHDとして「自分にできないことはできる人に頼る」という生き方でやり過ごしてきた僕にとって、仕事で助けてもらえるような関係性ではなくても、もう少し気軽に話せる知人は探しておかなきゃいけないようにも感じています。
AIの登場で加速した緩慢な孤独への対抗策として、対面でのやり取りの重要性に気がついたところで、既に手遅れかもしれませんが、今さらながら「飲み会とか勉強会とか」の価値を真剣に考えています。