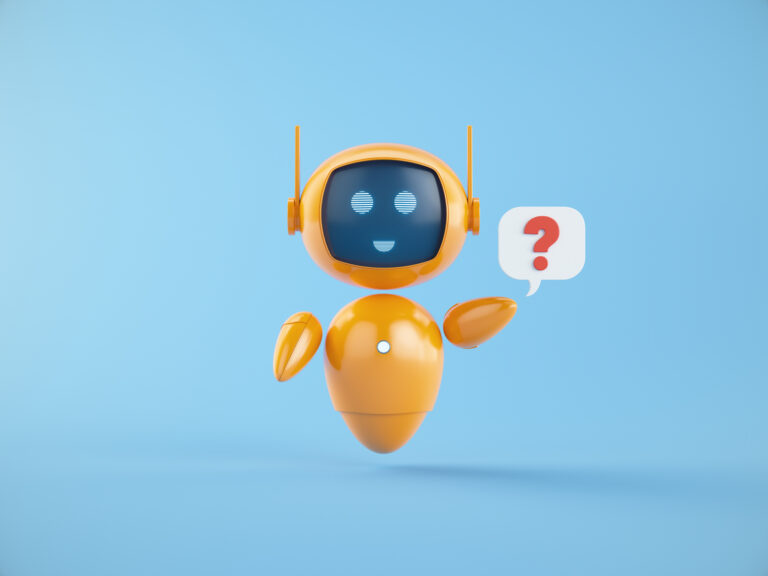大阪府から山口県に引っ越しをして15年以上が経過しました。いまだに、自分のことは「関西人」だという自負はありますが、正しくは奈良県奈良市出身です。
ケーブルカーに乗れる生駒山上遊園地、あやめ池大劇場があった近鉄あやめ池遊園地(2004年閉園)、鹿だらけの奈良公園を遊び場として育ちました。また、近鉄西大寺駅の分岐器の複雑さは一部で有名なようですが、それを何とも感じないぐらいの日常の光景として過ごしていました。
山口県と奈良県が近距離というわけではありませんが、新幹線に乗れば新山口駅から新大阪駅まで1時間40分程度のため、3時間もあれば奈良県に行くことができます。
ただ、僕と両親は僕が子供の頃から互いの関係性に微妙な問題を抱えており、心の距離が非常に遠いため、今の僕にとって奈良県がそんなに近いわけではありません。
あ、僕は楽しくやっていますので、どうかご心配いただきませんように。僕がADHDということは、両親は心理検査を受けていませんが、その可能性が高く、家族というか、血の繋がりがあるゆえに色々ある感じです。
それでも望郷への思いがないわけではなく、奈良ナンバーの車を見かけたら声をかけてしまいそうになるほどに、山口県の中に関西や奈良県の雰囲気を無意識に探してしまいます。
そこで今回は、これまで僕が見つけた山口県の中の奈良県をご紹介したいと思います。
なお、僕が山口県で感じる奈良県の感覚は、山口県で暮らす大分県別府市出身の方が、山口県美祢市秋芳町にある別府弁天池を見て「わぁ!なんか大分県っぽさがある」と感じているぐらいのゴリ押しに近い可能性があることに留意してください。
東大寺の大仏の材料は山口県から来たらしい
「奈良の大仏」としても有名な奈良県奈良市にある東大寺大仏殿に安置されている盧舎那仏像は752年に完成したとされていますが、その鋳造に利用された銅は現在の山口県美祢市の長登銅山で採掘されたものが利用された可能性が高いとされています。
そのことから、長登銅山は「奈良の大仏のふるさと」として知られているそうですが、幼少期から奈良公園を庭のようにして遊んでいた僕には全くの初耳でした。
それはさておき、長登銅山は奈良時代の7世紀から8世紀頃に採掘が始まったと考えられ日本最古の銅山と考えられ、その後もコバルトの採掘や精錬所として1960年代の閉山まで、東大寺建立の国家的事業から明治時代初期の近代鉱業を長きに渡って支えてきました。
その様子は長登銅山文化交流館で詳しく知ることができるようですが、僕はまだ行ったことがないため詳しくお伝えすることができません…奈良県奈良県と言いながら行ったことがないとか、ほんまごめんやで。
さて、奈良県奈良市との繋がりは銅だけではありません。山口県山口市の街並みにも、故郷の面影を感じることがあります。
大内氏の歴史に明るくない僕なりの理解になりますが、第9代当主だった大内弘世氏が当時貿易を行っていた朝鮮や明の文化と京都の文化や街並みを参考に融合して発展させた文化や街並みを「大内文化」だと理解しています。今でも大内文化の名残を残す地域は「西の京」と呼ばれており、歴史を感じさせてくれます。
特に瑠璃光寺から十朋亭維新館周辺はどことなく京都や奈良町の雰囲気が感じ取れ、それとなく故郷を感じさせてくれます。
また、大内文化の影響を受けているのなら瑠璃光寺の五重塔は、京都の東寺の影響を色濃く残しているのかもしれませんが、僕にとって瑠璃光寺の五重塔は東寺や奈良の興福寺五重塔を思い起こさせます。
東大寺の歴史的な影響力を感じる
山口県防府市にある阿弥陀寺は、平安時代末期の「源平の争乱(治承・寿永の乱)」によって焼失した東大寺の再建のため、東大寺大勧進職として、彼の地を訪れていた重源が現世安穩を祈るために自ら荒野を切り開き、周防別所として創建した寺とされています。
そのため、阿弥陀寺の駐車場手前には「東大寺別院」と彫られた寺号標が設置されています。
テセウスの船で考えると当時の材料は残っていないようにも感じますが、阿弥陀寺の境内には東大寺の再建に従事する労働者の保養として利用された「石風呂」の遺構が残されています。今でも定期的に保存会によって石風呂が焚かれているそうです。
また、山門には国指定重要文化財でもある2躯の木造金剛力士立像が安置されています。仏師は「東大寺の仁王さん」の愛称でも親しまれている南大門金剛力士像を造像した快慶一派ではないかと考えられています。
難しい話はこれぐらいにして、長登銅山にしても、阿弥陀寺にしても、奈良県を遠く離れて、山口県で「東大寺」の名前をこんなに目にするとは想像しておらず、図らずも平安時代や鎌倉時代の東大寺の影響力を感じることになりました。
阿弥陀寺は「あじさい寺」とも呼ばれ、6月頃には4000株を超える紫陽花が楽しめるそうです。僕はまだ紫陽花の開花時期に阿弥陀寺に行ったことはないのですが、きっと奈良県桜井市にある長谷寺のように綺麗なんだろうと想像しています。
家族旅行といえば和歌山県だった
「お前は山口県にある奈良の欠片を探すんじゃないのか?」と怒られそうですが…山口県山陽小野田市の権現山の山頂には、和歌山県の熊野三山の流れを汲む熊野神社があります。
僕の幼少期は、家族で旅行と言えば祖父母が好きだった和歌山県の那智勝浦町でした。そしてほぼ毎回、熊野那智大社に参拝し、那智の滝を見るのがお決まりのコースでした。熊野三山には、僕の幼少期の思い出がたくさん詰まっています。
今ではすっかり遠くなってしまった熊野三山への思い出に浸ろうと訪れた熊野神社は、決して広大な境内ではないものの、静寂に包まれていました。権現山の山頂にあるため、どことなく那智山にある熊野那智大社が思い出されます。
ただ、熊野神社は熊野那智大社ではなく、和歌山県田辺市にある熊野本宮大社、和歌山県新宮市にある熊野速玉大社の流れを汲む神社のようです。
そして、熊野神社の境内には東大寺大仏殿の柱の穴をくぐり連想させる「日本一小さい鳥居」があります。「奈良県の欠片」というよりは、「思い出の欠片」に近いですが、熊野神社に故郷への思いを重ねています。
「せんとくん」を補充する
せんとくんとは、2010年に奈良県奈良市開催された「平城遷都1300年祭」のキャラクターで、彫刻家の籔内佐斗司氏によってデザインされました。
籔内氏はせんとくんを図案化する以前からも、せんとくんによく似た童子の作品を数多く残しており、そんな作品の1つ「蜘蛛のいと」が山口県宇部市のときわ公園に野外展示されています。
この作品は、芥川龍之介の小説「蜘蛛の糸」をモチーフにしているようで、せんとくんによく似た童子が蜘蛛から垂れ下がった糸に向かっていく姿が展示されています。
僕は、せんとくんが不足してくると、ときわ公園の「蜘蛛の糸」を眺めることで、せんとくんを補充しています。
近鉄と再会できた
山口県に移住後の最大の衝撃は防長交通が近鉄グループだったことでした。青色と黄色の配色の防長バスは近鉄バスのカラーリングをそのままに車両後部の「KN」を塗りつぶしただけの状態で運行されています。
青色と黄色の配色の防長バスを初めて見かけた時の「なんでここに近鉄バスが走ってんの?でもなんか違うな…近鉄バスから中古のバスを購入してるのか…?」と疑問に感じていました。
もう近鉄には会えない人生だと覚悟を決めていた僕にとって「まさか…こんな場所で近鉄に再び会えるとは…」という衝撃は、今このブログを読んでいる方が感じている衝撃の数十倍、数百倍に匹敵します。
なお、僕にとっての心の電車は近鉄(近畿日本鉄道)ですが、僕にとっての心のバスは近鉄グループの奈良交通です。そのため、近鉄バスのカラーリングにはそこまで心が震えなかったことが本当に悔やまれます。
近鉄百貨店の包装紙に包まれた僕の思い出
残念ながら2013年に惜しまれつつ閉店しましたが、徳山駅近くに近鉄松下百貨店がありました。長年、近鉄松下百貨店を利用してきた周南市民以上に、近鉄松下百貨店の閉店を寂しく感じていた元奈良県民が山口市にもいました。
日々の買い物や誕生日プレゼントを買ってもらった思い出の中心にいつも「近鉄百貨店 奈良店」がありました。そのため、包装紙や紙袋に特別な思い出を重ねていたのかもしれません。
山口県に移住後、近鉄百貨店の包装紙を眺めたいという他人からすれば不可解な理由で、何度か近鉄松下百貨店に買い物に行ったこともありました。
近鉄松下百貨店の跡地は2021年には取り壊され、現在、徳山駅前周辺の再開発が進んでいます。徳山駅前周辺の土地勘がない僕にとって、どこに近鉄松下百貨店があったのかも思い出せません。
それでも、徳山駅前にあるビルの壁に取り付けられた「近鉄徳山ビル」の箱文字を眺めながら、故郷への思いを馳せています。
最後に
20代ギリギリで住み慣れた関西から山口県に移住をした僕にとって、移住直後はハンズもロフトもなく、22時台に終電というこんな場所でやっていけるのか不安と不満で一杯でした。
また、大阪に引っ越しをするまでは、奈良県奈良市で生活していたこともあり、東大寺や西大寺、興福寺、唐招提寺に囲まれて過ごし、当時の僕は山口県の神社仏閣になんの興味もありませんでした。
しかし、この15年以上の長い年月の中で、少しずつ山口県にある奈良県の痕跡を探し続けた結果、その多くは古くからそこにあり、山口県の方々が長年守り繋いできた神社仏閣ばかりでした。
20代、30代は神社仏閣にそこまで興味がなかったものの、30代後半になるとナスの煮浸しのような滋味深いものの良さが分かるようになると聞きますが、それと同じように、神社仏閣の良さに気がつき、気がつくと御朱印帳を持ち歩くようになっていました。
正直なところ、山口県の中で奈良県の欠片はそこまで多くはありません。それでも、奈良県の欠片を関西の欠片に拡大して、和歌山の熊野三山や京都で起きた禁門の変(蛤御門の変)に望郷を感じてみたりしながら、これからも「奈良県の欠片」を集めていこうと思います。