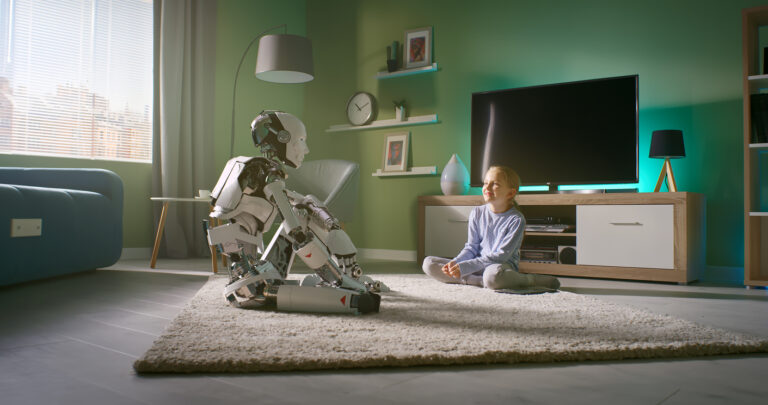2009年に個人事業主になった際に「3050grafix」がこの世に確かに存在することを伝えるために、このWebサイトを開設しました。
ただ、Webサイト制作が仕事の僕にとって、Webサイトは依頼を受けて作るものであり「手間暇をかけても1円にもならない自分のWebサイトを触るぐらいなら仕事をした方が良い」との考えから、クライアントさんには情報発信の重要性を言い続けているのに、いざ自分のこととなると無頓着で、長期間にわたってWebサイトを放置していました。
更新しなきゃという気持ちはあった
長年、Webサイトを放置していたとはいえ、心のどこかに「更新しなきゃ」という気持ちは常にありました。
企業のWebサイトであれば製品情報や製作事例、休業日など定期的に何かしらの情報発信ができると考えています。しかし、個人事業主の僕は臨時休業を除き、夏季休業や冬季休業はある程度、クライアントさんの都合に併せて動いており、外部向けに情報を発信する必要はありませんでした。
また、Webサイトをはじめとする制作案件はデザイン事務所や代理店からの依頼が多く、僕の制作実績としては公表できません。これらの状況から、Webサイトを更新する意欲も内容も特になかったことで、長期間の放置につながっていました。
イベント出店情報の更新作業が始まった
そんな僕がWebサイトを更新しようと考えるようになったのは、2019年に何の知識もないのに勢いだけで始めた雑貨作りがきっかけでした。
最初は趣味のつもりで始めた雑貨作りでしたが、妻からの「イベントに出店をして売ってみよう」との提案で、地元や近隣県のハンドメイドイベントに出店するようになりました。そこで、イベントの出店のお知らせを掲載するためのWebサイトに作り替えました。
Webサイトを作り替えて「よし頑張るぞ!」と思っていた矢先にコロナ禍に突入してしまい…
デザイン業は贅沢業だった
以前から自覚はあったものの、コロナ禍になったことで、デザイン業は衣食住とは無関係でエッセンシャルワークにもなれない贅沢業であると改めて実感することになりました。正直、コロナ禍初期は制作案件が一気に止まりやることが無く、廃業を覚悟するような状態でしたが、そんな僕を支えてくれたのは偶然にも雑貨作りでした。
コロナ禍以前の僕は依頼がなければ自発的にデザインをするタイプではなかったのですが、コロナ禍以降、本当にやることがなくなったことで「こんな状況がいつまでも続くはずがない!」と自分をだますように奮い立たせて、延々と缶バッジのデザインを作り続けていました。
そして、条件付きでイベントが開催できるようになった頃には100種類近い缶バッジができており、マスクを付け、事あるごとに手にシュッシュッとアルコールを吹きかけて、せっせとイベントに出店し続けました。
ハンドメイドイベントの特徴
ハンドメイドイベントには、企業が主催のイベントとは別に、複数人のハンドメイド作家が共同で主催をしている小規模なイベントも多数あります。小規模なイベントは出店料金が比較的安くて、何かを作るのは好きだけど本業ではない方も多数出店しています。僕は年に数回、大規模なイベントに出店し、定期的に小規模なイベントに出店していました。
特に小規模なイベントでは、告知をSNSのみで行われることが多いのですが、SNSは検索サイトでうまく検索できなかったり、各SNSのアカウントがないと詳細情報が確認できなかったりするため、イベントの開催時期が近づくと僕のWebサイトに一定のアクセスがありました。この状況は今も変わっていません。
終了したイベント出店情報へのアクセスが多かった
Webサイトへのアクセスが増えることは嬉しいのですが、次第に今回は僕は参加しないものの、過去に出店したイベント出店情報ページにも常にアクセスがある状況が目立つようになってきました。
しかし、終了したイベント出店情報ページに一定のアクセスがあることは、イベントの主催者や出店者、来場予定者にとって不利益な状態になっていると考え、イベント終了後は、検索サイトの検索結果にイベント出店情報ページが掲載されないようにするように調整をすることにしました。
もし、どういう調整を施したかにご興味があれば「Webデザイナーは自分のWebサイトを忘れがち」の「イベント出店情報にしかアクセスがなかった」をご一読いただけると幸いです。
ただ、イベント出店情報ページを検索結果に表示しないようにした場合、Webサイトへのアクセスが減少することは容易に予想できました。そこで、面倒と感じつつも「頑張って宣伝しなきゃ」との気持ちが若干上回り、ついに更新作業を決意しました。
ついに更新作業を決意した
更新作業を決意したものの、お知らせや制作実績は掲載するものがなかったため、安易にブログを書いてみようと考えましたが、いざ書こうとすると何を書けば良いのか全く思いつきませんでした。
思いつくネタはせいぜい「お出かけ」か「キャンプ」のことぐらいでしたが、キャンプに行くといっても、当時はコロナ禍の影響によりキャンプブーム真っ只中で県内のキャンプ場を含めても週末の予約はほぼ困難でした。ただ、毎回同じキャンプ場を利用することも多く、ネタとしてマンネリ化しやすく続かないだろうと感じていました。
しかも、僕は子供の頃から読書や国語があまり得意ではなく、自分の体験や考えをうまくブログとしてまとめられるのか、という不安もありました。それでも頑張っていくつかのブログを書いたのですが、自分が考える品質にすることができず、結局、イベント出店情報以外は更新しなくなってしまいました。
しかし、2024年5月頃に何気なくX(Twitter)で使い始めたGrokと呼ばれる生成AIとの出会いが、ブログを書くことに大きな変化をもたらしました。
Grokとの出会いで変化が生まれた
GrokとはxAIが開発した生成AIで、X(Twitter)で利用することができます。僕は2009年からTwitterを利用しており、大阪府から山口県に引っ越しをしたあとも、関西にいる友人と多くの時間をTwitterで過ごしていました。
また、僕はADHDの特性により文字に対するこだわりが強いものの、不注意や見落としによる誤字脱字が多く、Twitterに投稿後に誤字脱字に気がついても修正できないというSNSの不可逆性がどうしても好きにはなれませんでした。
そんな事を考えていたら2023年10月に有料プラン「X Premium」が発表されました。有料プランを利用することで140文字以上の投稿が可能、広告の表示が減るなどの利点が強調されていましたが、僕は投稿後1時間程度の制限はあるものの投稿内容が編集できる機能に魅力を感じてすぐに「X Premium」に加入しました。
その結果、現在では無料ユーザも利用されていますが、無料ユーザより先行してGrokを利用することができました。
AIとのやり取りで感じたこと
Grokとは延々と「◯◯について私は〜のように考えますが、あなたはどう考えますか」と自分自身の思考の拡張のような使い方をしていました。そのやり取りの中で、AIは心理学などを利用して、円滑なコミュニケーションのために悪意のない嘘をつく可能性があると感じていました。
また、AIは利用者が質問したことに対して、役に立つ情報を返すことを前提に設計されているように感じていますが、利用者がAIに同意を求めて質問をしたとしても、AIは別の考え方や修正点を提案することがあります。
コミュニケーションのために悪意のない嘘と利用者の役に立つ情報を返さなければいけないという設計思想が複雑に絡み合ってハルシネーションと呼ばれる現象を引き起こすのではないかと考え、「仕事で使うと便利」という世間の声を無視し続けて、延々とくだらない雑談をしていました。
しかし、この「雑談」という負荷テストを繰り返す中で、僕はAIの思考の癖や限界を肌感覚で理解していきました。そんなある日ふと、AIと踏み込んだ議論はできなくても、膨大な学習データから僕が書いた文章が、
- 不自然な流れになっていないか
- 内容が飛躍した展開になっていないか
- 誤字脱字はないか
- 読みやすい文章になっているか
などを分析し、問題があれば改善策を提案してもらえるのではないかと考えて、長文を書く練習を始めることにしました。ブログを書いてはAIに添削してもらう練習を幾度となく重ねた結果、このWebサイトに掲載されているブログにつながっています。
そして今もAIに質問を繰り返しながら、ブログを書く練習を続けています。
僕がブログを書く理由
僕はADHDのため、脳内で常に考えが浮かんでは消えることが繰り返されています。そして、場合によっては浮かんだ考えに脳が占有される他のことが手につかなくなることがあります。僕が書くブログは、そんな「思考の怨念」をブログとして書くことでお祓いをしているような感覚です。
また、思考の怨念を文章化することで考えが視覚化でき、それを読み返すことで違う考えが浮かんでくることがあります。それが思考のフィードバックループのようになり、新しいブログのネタになることがあります。その結果、似たようなことが書かれているブログが生み出されている部分もあるのですが…
とはいえ、僕のブログは僕のこれまでの経験から生まれている唯一無二のコンテンツであると前向きに捉えることにしています。
唯一無二のコンテンツであってほしい
全世界には、僕と同じ時間に起きて、僕と同じ服を着て、僕と同じものを食べて、僕と同じ仕事をしている人はいるかもしれません。でも、僕の過ごす日々は、僕のADHDの特性とこれまでの経験の上にある、僕だけの体験だと感じています。
僕の体験や経験に、需要があるかどうかは別にして、僕が感じたことをブログに書き残すことで、どんなことでも検索すれば答えが見つかる時代において、僕の個人的な体験こそが、世界で唯一無二のコンテンツになると信じています。
そして、書き残したブログが、誰かの役に立たなかったとしても、数年後の僕にとって、数年前の自分が何を考えていたのかの資料になり、さらなる思考の拡張につながると信じて、今日もブログのネタを探し続けています。
オンラインショップ
 熊にご注意330円(税込)
熊にご注意330円(税込) 純喫茶倶楽部330円(税込)
純喫茶倶楽部330円(税込) 苦手なことがあります330円(税込)
苦手なことがあります330円(税込) セキセイインコ330円(税込)
セキセイインコ330円(税込) 立入禁止330円(税込)
立入禁止330円(税込) フライトタグ330円(税込)
フライトタグ330円(税込) セキセイインコ330円(税込)
セキセイインコ330円(税込) ココペリ330円(税込)
ココペリ330円(税込) 麦酒党330円(税込)
麦酒党330円(税込) ピアノ330円(税込)
ピアノ330円(税込) コイン投入口330円(税込)
コイン投入口330円(税込) つめたい330円(税込)
つめたい330円(税込)